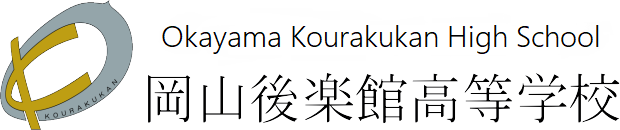
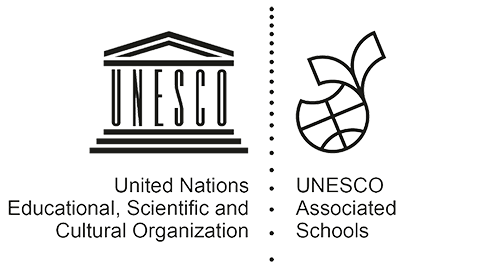 〒700-0807 岡山市北区南方一丁目3番15号
〒700-0807 岡山市北区南方一丁目3番15号TEL:086-226-7100 FAX:086-226-7109
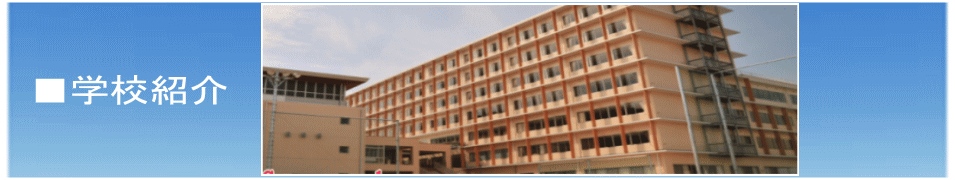

校長 矢吹 玲子
四月には、好奇心溢れる表情で期待に胸を膨らませた新入生が、おろしたてのまだ馴染まないスーツの下に不安で落ち着かない心を隠しながら、岡山後楽館高校に入学してきます。三月には、安心と達成感と自信と寂しさを抱いて卒業生が巣立ちます。
生徒たちは、岡山後楽館で過ごす三年間に何を経験し、何を学び、どのような変化を見せてくれるのでしょう。サナギが大きくて美しいはねを持つ揚羽に変わるように、ヤングアダルトが頼もしく逞しい生きる力を持った社会の創り手になっていく、人生において最も大きな変化を遂げる場所こそ、私たち高校教師が関わっている「学校」なのだと感じます。
生徒がこれから歩んでいく未来は、私たち大人が自身の人生の中で体験したことのないような予測困難なものであり、それゆえ教師が「教える」ことには限界があります。むしろ生徒が自ら「学ぶ」場面をいかに多種多様に準備できるかという点において、これからの学校の真価が問われることになるのだと感じています。そして、彼らが高校時代に学んで身に付けることが期待されているものには、大人の私たちが持っていないような資質や能力さえも含まれているということを、教師は認識しておくべきでしょう。そう考えると、同水準の目標に合った同質の生徒集団を作ろうとする指導は、これからの教育が目指すところとは言えません。
こうした考え方に基づいた高校教育改革を、結果的に加速させることになったのが、未曾有のコロナ禍でした。あらゆる活動が制限された三年間に、私たちは従来の教育活動一つ一つの意義を問い直し、その方法を考え直す機会を得ました。授業における実習やグループ活動、講演会や施設見学、式典や文化祭・体育祭や修学旅行などの学校行事、海外交流事業、部活動など、数え上げればきりがありません。このとき私たちは、学校教育とは他者とのコミュニケーションでできているということを身に染みて思い知ったのです。大人になる準備のための時間を過ごす高校において、必須と言えるものこそが、コミュニケーションによって成り立つ「協働」の体験であることを意識させられたのです。
岡山後楽館高等学校では、社会の様々な世界や分野で生きている人々と出会い、心を揺さぶられ、喜びを感じられるような機会を、生徒に提供していくことを大切にしたいと思っています。そのために本校の特色として重点的に取り組んでいる教育活動を紹介します。
まず、「岡山の未来」と冠した総合的な探究について。学校経営目標に挙げた「自他を尊重する心の育成と社会に貢献する人づくり」に資するべく、特に地域を学びの場として、生徒が自分と社会とのかかわりや自らの役割を認識できる教育の推進を目指しています。社会総がかりで子どもにかかわるという使命を担う学校運営協議会(コミュニティースクール)の委員として、生徒への学びの場の提供という活動実績のある地域団体や企業等の代表の方を委嘱し、積極的・具体的な教育活動への参画の可能性を協議してきました。もちろんこれまでも本校では、シティキャンパス構想として岡山市の行政機関や社会教育機関などをはじめ、地域の団体や大学等からの絶大なる支援を得て、生徒は数多くの選択肢の中から自分の興味関心に応じた学習体験をしてきました。
次に、「国際理解教育」について。本校では、英語・中国語・韓国語のそれぞれのネイティブスピーカー三人が、常勤のALTとして外国語の教鞭をとっています。授業の中にそれぞれの国の文化理解の活動を取り入れることで、生徒たちは日常的に国境を越えた文化や人々に接する機会を持ち、親しみと理解と興味を自発的に抱いていく姿が見られます。海外への訪問研修旅行、来日訪問団の受け入れ、オンライン交流など、様々な形の国際交流のメニューが提供され、生徒は自分にとって参加可能な活動に主体的に取り組むことができます。それらの活動を通じて、異なる文化や価値観に晒されることをごく自然なことと感じながら、世界中に友情の絆を結んでいます。
さらに、日常の様々な教科の授業においては、少人数の教室の中で生徒と対話をしながら授業を進めていくことにより、教師は生徒一人一人の理解の段階を把握しながら授業展開を工夫し、一方、生徒にとっては思考や議論を深めていく主体者としての自覚を体験させることを授業の目標としています。ICTの活用を工夫し、授業におけるコミュニケーションの形が圧倒的に多様化しています。溢れる情報の中から適切なものを選んで理論を構築していく練習が実施できるようになりました。
こうした生徒が自分で選んで体験できる豊富なメニューがあることが、岡山後楽館高校のモットー「自分で創る学校生活」を大いに支えていると言えます。まるで生徒は自らの興味関心に応じて、様々なメニューやチャンネルの間を自由に泳ぎ、ほしいものを手に入れながら自らの可能性を広げているかのように感じます。固定化されたカリキュラムではなく、まるで流動体の中で自由に泳ぎ回ることができるような「学び」の環境を創り上げた岡山後楽館高等学校の教育実践が高く評価され、令和五年度文部科学大臣優秀教職員組織表彰をいただきました。日頃の取組みに対して大きな励ましをいただいたことに感謝するとともに、未来に続く教育の方向性に確信をもって今後も「自分で創る学校生活」のための教育活動を一層充実できるよう、教師も努力を惜しまず学び続けたいと思います。
校長 矢吹 玲子
令和3年1月26日に中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』を目指して」が公表されました。日本が目指している新しい時代の教育というものが、我が岡山後楽館高校にとってはどのような意味を持ち、本校の教師は何を目指すべきか、そしてその教育体制の中では生徒のどんな活動が可能となるのかなど、常にそれらの目標を意識し見失わないようにして取り組んでいくことが大切だと感じています。新学習指導要領と「答申」を何度も読み返しながら、過去に歩んだ誰かの足跡を辿るのではなく、新たな足跡を自らが残していくという意欲と誇りを持って、日本の教師がこれからの学校教育を創り上げていくことが期待されているような、そんなメッセージを感じています。
「答申」の中で、令和の日本型学校教育とは「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学び」と定義されています。一方、岡山後楽館高校のスクールミッションには、「多様な生徒の個性を大切にしながら、生徒一人一人の自立に向かう成長を支える。」そして「他者との協働活動を通じて、自他を尊重できる持続可能な社会の創り手を育成する。」と宣言しています。創立以来「自分で創る学校生活」の建学の精神のもとでこれまで積み上げてきた本校の校風は、新学習指導要領の精神と非常に親和性の高い、目指す理念の一致するものであることに、感銘を覚え誇らしく感じます。開校当時に「こんな学校が日本に一つくらいあってもいいのでは」という思いを込めて、先進的な知見に基づいた信念と理想を貫いて本校を設置した岡山市教育委員会及び関係者に敬意を表します。
多様性と寛容が重視される現代そして未来を生きる若者には、高校教育を通じて、自分のよさや可能性を認識する機会が必要であり、そして同時に、他の人のことを価値のある存在として尊重する心を持てるようになることが求められています。本校では、後楽館高生になる前の中学生たちに対して、「何か自分の得意なこと、何か人より強く興味関心のあることを見つけて入学してきてほしい」と訴え続けています。現に後楽館高校では、様々な競技や部門で全国レベル、世界レベルで活躍している生徒たちを全校で応援しています。社会の中で不便や違和感を我慢して生活することを強いられている人々に寄り添いながらその課題を大人たちに向かって声を上げようとする生徒たちを教師たちが見守っています。外国の言語や文化を懸命に学び、海外の同世代の若者たちと深い感動と絆でつながった交流を続け、友情を育んでいる生徒たちの姿に平和な未来の姿を見ています。将来の社会の担い手としての「自分らしい生き方」と自らの役割の価値を見いだして、進学や就職へと全力で歩みを進める生徒たちを、私たちも全力で支援しています。
また、「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、生徒の興味関心に応じた履修科目選択や、少人数授業での対話を重視した学習が実施されています。授業中、教師は生徒に問いかけながら授業を進め、小グループでの意見交換や議論の機会が設けられ、各生徒の意見や感想がICTによりクラスに共有されています。学習内容に応じて、専門家が外部講師として招聘され、生徒は迫力のある本物の技術や専門知識を目の当たりにすることもあります。
本校は、長年のキャンディデート(申請中)の期間を経て正式に「ユネスコスクール」の認定を受けました。日本の教育におけるユネスコスクールが目指す教育効果はESD(持続可能な開発のための教育)の推進ですので、本校の従来の取り組みとの方向性は完全に一致していると言えます。日本ユネスコ国内委員会がガイドラインに示している通り、本校は海外との密接なネットワークを持ち、コロナ禍の3年間も絶えることなくグローバルな意見交換や発信を継続してきました。また、地域の企業、社会教育機関や行政機関、NPO等からの絶大な支援を背景に、直接社会とかかわり体験することのできる学びの場が維持されています。そして、校内外において意見を堂々と主張したり発信したりできる機会が設定され、気後れすることなく言葉で表現できる生徒たちが育っています。
このように、現在の本校の取り組みの状況は、とても大きな成果を上げ華々しく見えます。実際にこれらの実績が評価され、令和4年度岡山市教育功労賞、令和5年度文部科学大臣優秀教職員組織表彰をいただきました。身に余る光栄と感じつつも、認めていただくことで職員生徒一同、大いに励まされています。その一方で、「令和の日本型教育」の実現は、教師に高度な知見とスキルが要求されるものであり、真の意味での教育効果の高い学びの場を提供し続けることは、長年教育に携わってきた経験豊かな教員にとってすら、非常に大きな負担を強いるものであることも否めません。
令和の岡山後楽館型教育のスタートを切った今、大切なことは、目指している理念が何であるのか、判断の拠り所とするべき理念が何であるのかという意識を、教員も生徒も保護者も、学校にかかわるすべての関係者が共有し、常に確認し合いながら維持していくことではないかと思っています。令和4年12月19日に公表された、「『新たな教師の学びの姿』の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成」と題した中央教育審議会答申では、目指すべき教師の姿として、改めて「教職生涯を通じて学び続けている」、「子供の主体的な学びを支援する伴走者としての能力も備えている」、「教師自身も志気を高め、誇りを持って働くことができている」などが挙げられています。そして一人一人の教師が個々の生徒の多様な教育ニーズに対応した学びを提供するだけではなく、学校自体が子供たちの多様性を受容でき、それに対応できる組織になっていることが大切であると述べられています。良質な教育の提供と教師の負担軽減のためには、一人一人の教師が学び続けること、それも「主体的・対話的で深い学び」を教師自身の学びの姿とすることが大切であると考えています。
校長 矢吹 玲子
令和三年度、学校教育法施行規則の一部改正に基づいて、高校に期待される社会的役割等(いわゆる「スクールミッション」)を設置者である岡山市が再定義しました。本校のスクールミッションは次の通りです。
「自分で創る学校生活」の建学の精神のもと、単位制総合学科の特色と中高一貫教育校の強みを生かし、多様な生徒の個性を大切にしながら、生徒一人一人の自立に向かう成長を支える。
地域や世界とつながり、他者との協働活動を通じて、創造力、論理的思考力、表現力を伸ばし、自他を尊重できる持続可能な社会の創り手を育成する。
創立以来大切にしてきた建学の精神を、生徒は学校生活の根幹として常に意識しながら、主体的な学校生活を送っています。明文化された校則に縛られるのではなく、一つ一つの言動や振る舞いをする前に、それが正しいことか、適切な作法であるかを、自分で考えて判断することは、実はとても難しいことです。本校はその難しい判断を、生徒にもそして教師にも課しているというわけです。高校生は管理され保護されるだけの子どもではなく、信頼され判断を任される若き大人(ヤングアダルト)として扱われる一面があるはずです。「若き大人」である生徒が周囲の雰囲気に流されることなくしっかりと自分で考えて出した結論を、教職員は尊重し見守っていきたいと思います。
本校のもう一つの特色は、単位制総合学科中高一貫教育校ということです。工業のものづくりに打ち込む生徒、簿記の技能を高めることに専心する生徒、大学進学を目指す生徒など、ほかにも色々な専門教育を受けている生徒が同じ空間の中でクラスメートとして生活を送り、共に協働して「総合的な探究」のチームを組み、力を合わせて学校行事を創り上げていくのです。将来、宮大工を目指す人と看護師を目指す人との関心の領域は違うでしょう。教員免許取得を目指す人とダンスのプロを目指す人との大切にしたいものも違います。13歳の中等部1年生が情熱を傾けるものと18歳の高等部3年生が夢に描くものももちろん違うはずです。それらが価値観や考え方の違いというものなのです。
学校という環境が多様な生徒がともに過ごしている場所となっています。実はそれは、現実の社会そのものに近い状態なのだろうと思うのです。社会に出て生活をすれば、そこには色々な考え方、生き方の人がいて、異文化のバックグラウンドをもつ人たちとともに暮らしていくことになります。本校において生徒はそのような社会の縮図を体験していると言えるのかもしれません。たくさんの人々が皆それぞれ違った考え方やマナーの基準をもち、お互い傷つけないように気持ち良く生活していくためには、その都度周囲の状況をよく考えて判断しなければなりません。その時に、忘れてはいけないのが「自分の価値観や基準を他の人に強制してはいけない。考え方の違う人を排除してはいけない。」という社会のルールです。自分が知らず知らずのうちに、相手やほかの誰かを不快にしたり居心地悪くしたり、傷つけたりするような言動や振る舞いをしないための練習、それが後楽館の大切にしている「社会のルールとマナー」なのだと思うのです。
後楽館が包含する多様性はさらに幅広いものです。他校では当たり前の男女に分けられた統一の制服をもたないことで、意識をジェンダーから個々の人へと向かわせ、バリアフリーとユニバーサルデザインの環境が、身体的や精神的なハンディキャップを解消へと近づけていると信じています。色々な個性や特性をもった人々がごく自然にそばにいて、お互いに言葉を交わしながらお互いを知っていくという、この環境こそが後楽館が維持していくべき教育の土壌なのだと思います。
未来に向かうこれからの教育において、子どもたちが身に付けることを求められている力は、差し出された課題を「解決する力」ではなく、何が課題であるのかを「発見する力」だと言われています。課題とは言い換えると「違和感」として感じられるものであり、違和感は同質的集団の中からは発生しないのです。多様性(ダイバーシティー)の重要性が叫ばれるのはまさにそのためでしょう。後楽館の教育環境そしてスクールミッションに込められた教育理念は、多様性から生み出される新しい価値の創出を可能にし、そこでは自身の信念と他者への尊敬の念を兼ね備えた若き大人が育つ —― これが、後楽館という唯一無二の教育モデルであると思っています。
岡山市立岡山後楽館高等学校
〒700-0807 岡山県岡山市北区南方一丁目3番15号
TEL:086-226-7100 FAX:086-226-7109
本サイトは、岡山市立岡山後楽館オフィシャルホームページであり、岡山市立岡山後楽館によって管理・運営されています。
本サイトの内容を、権利者に無断で複製・改変および放送・有線送信等に利用することは固く禁止します。
Copyright(C) OKAYAMA KORAKUKAN ALL RIGHTS RESERVED.